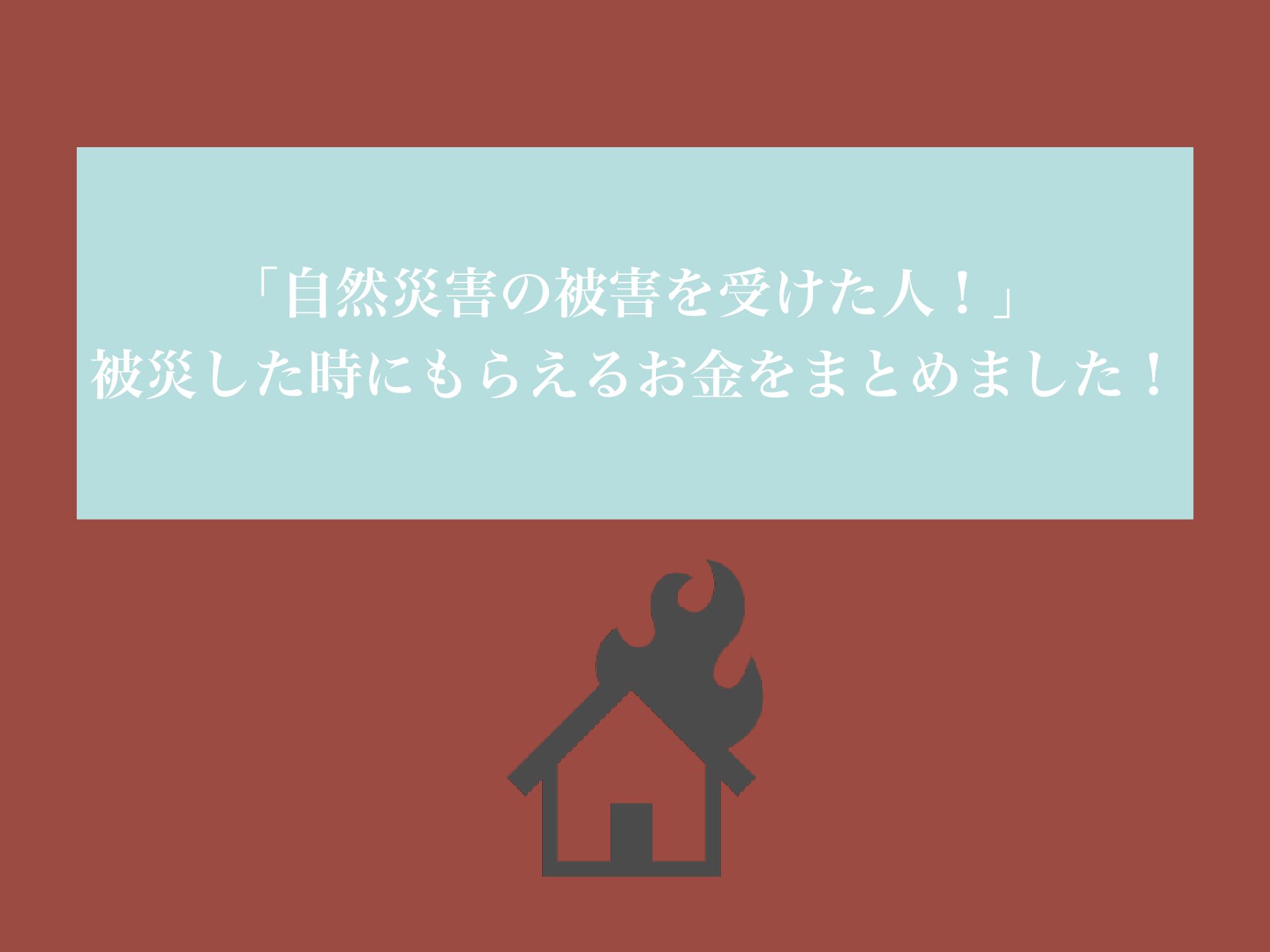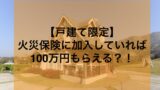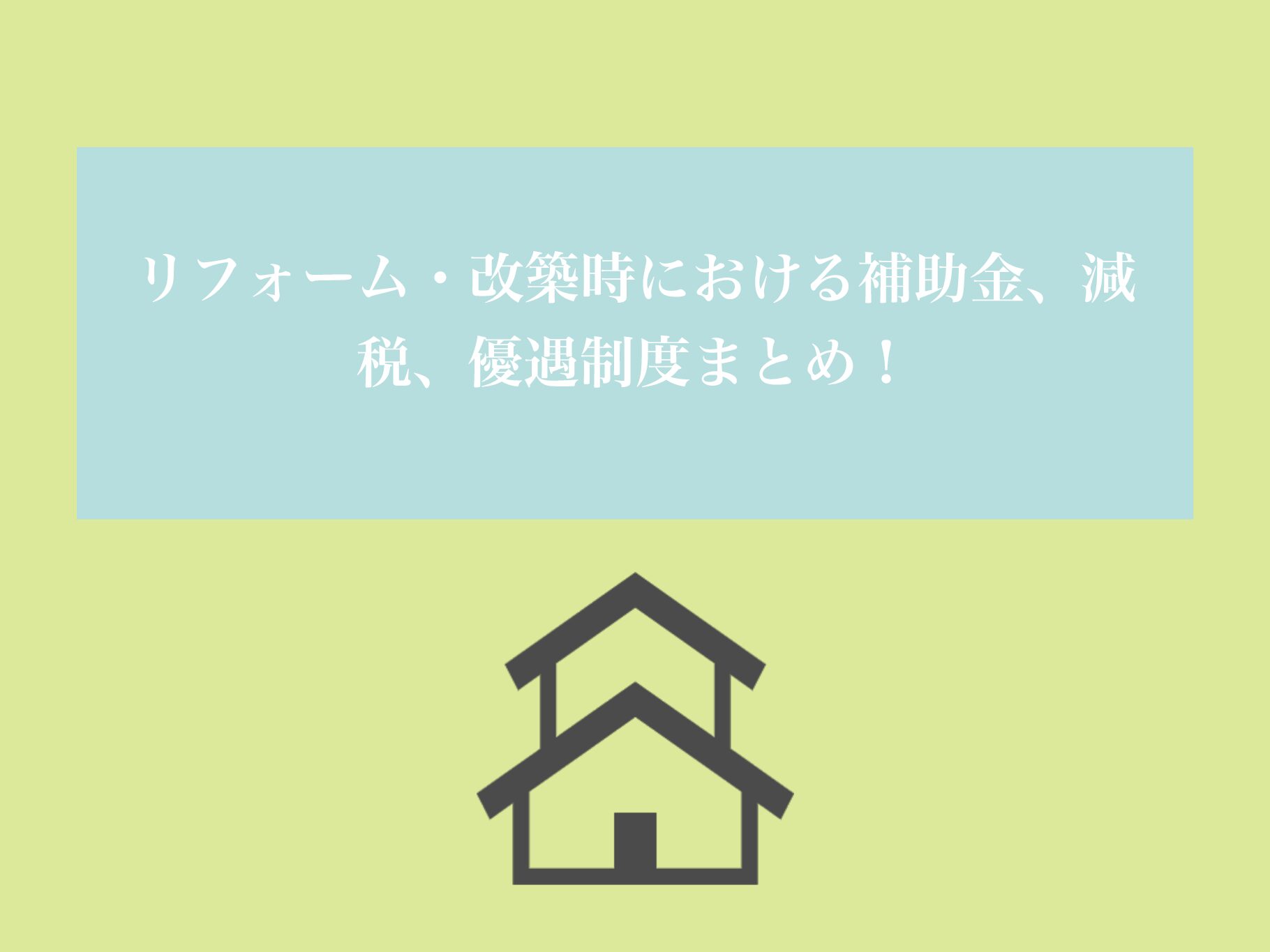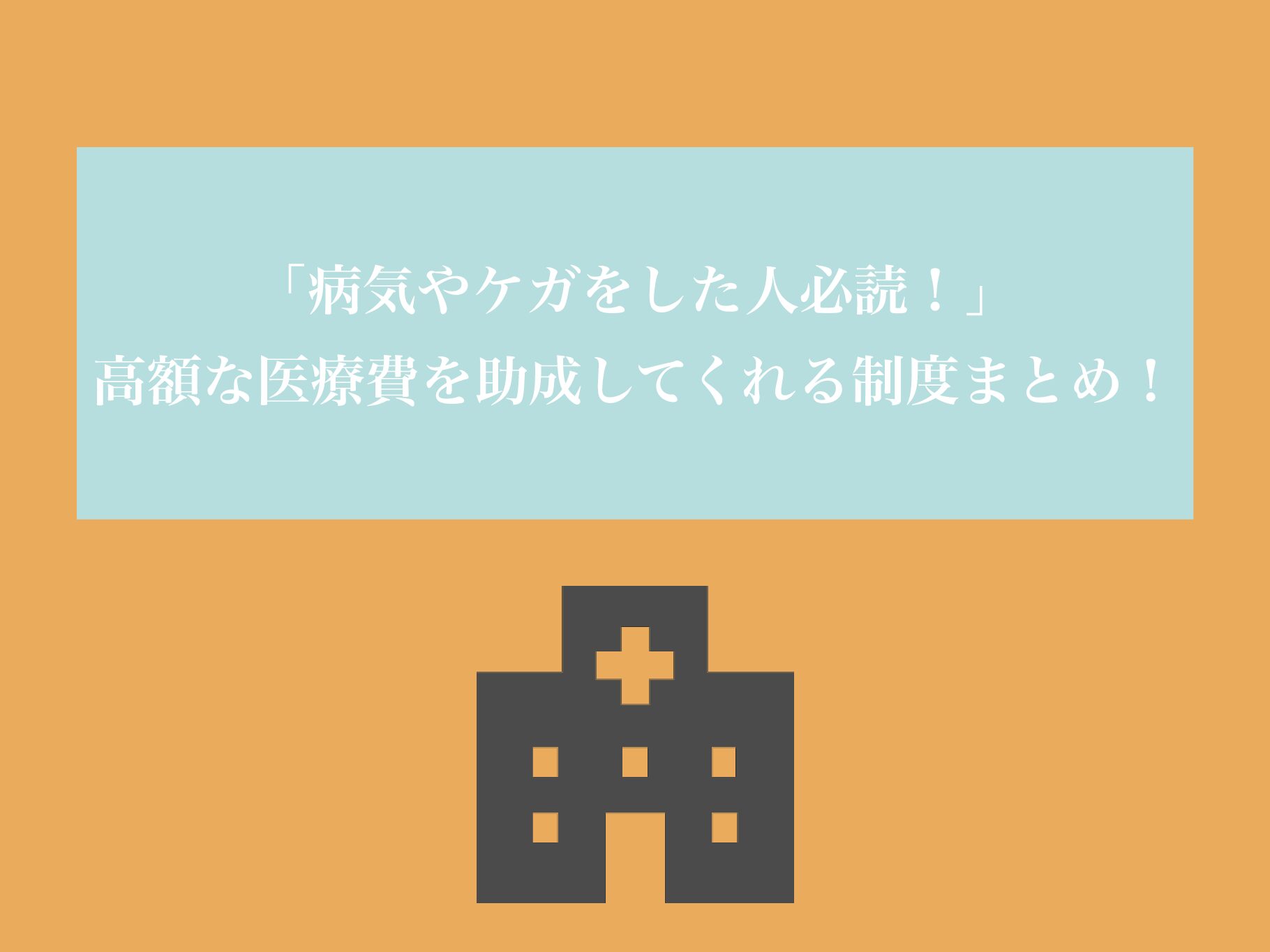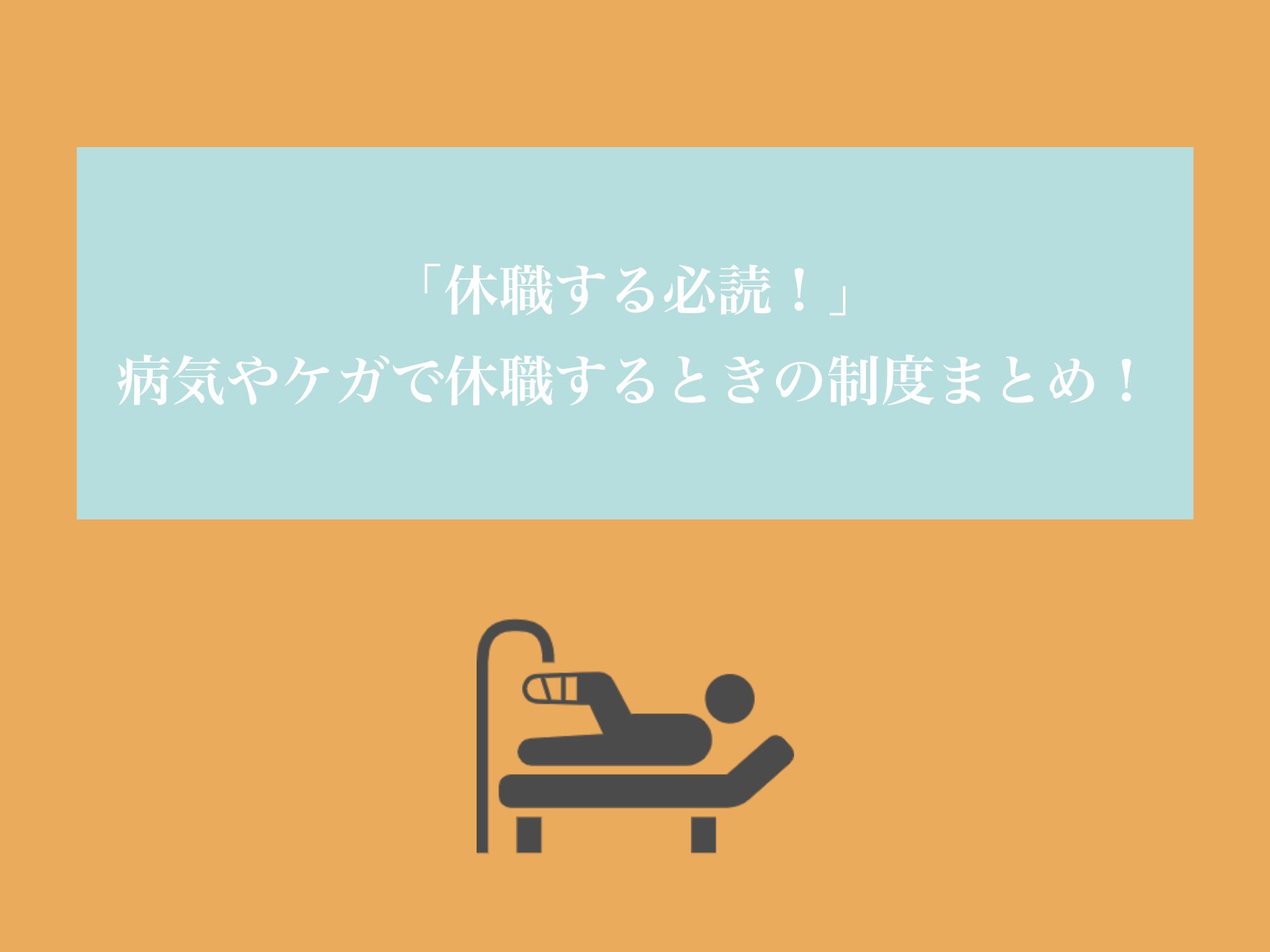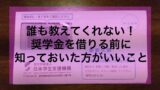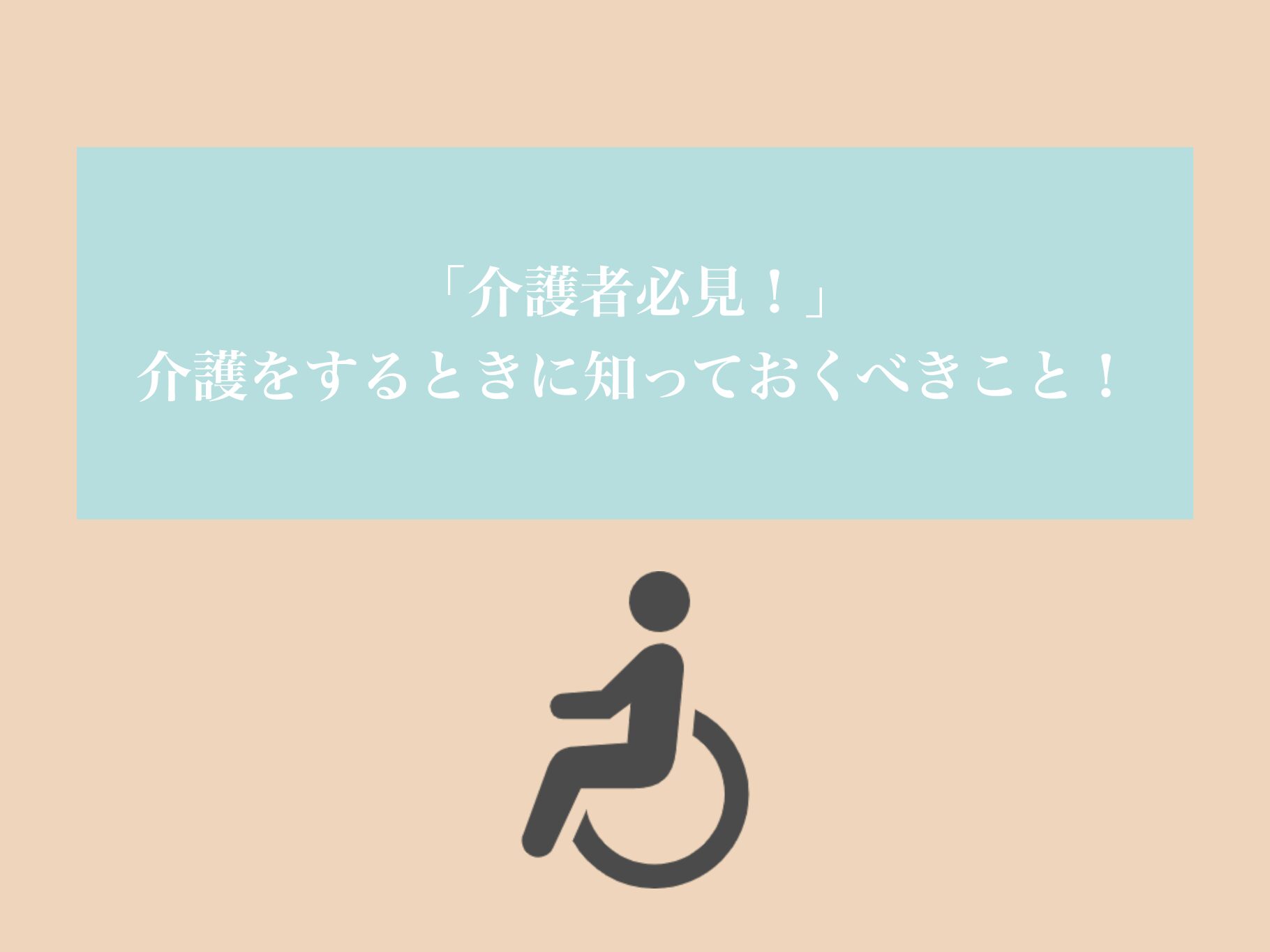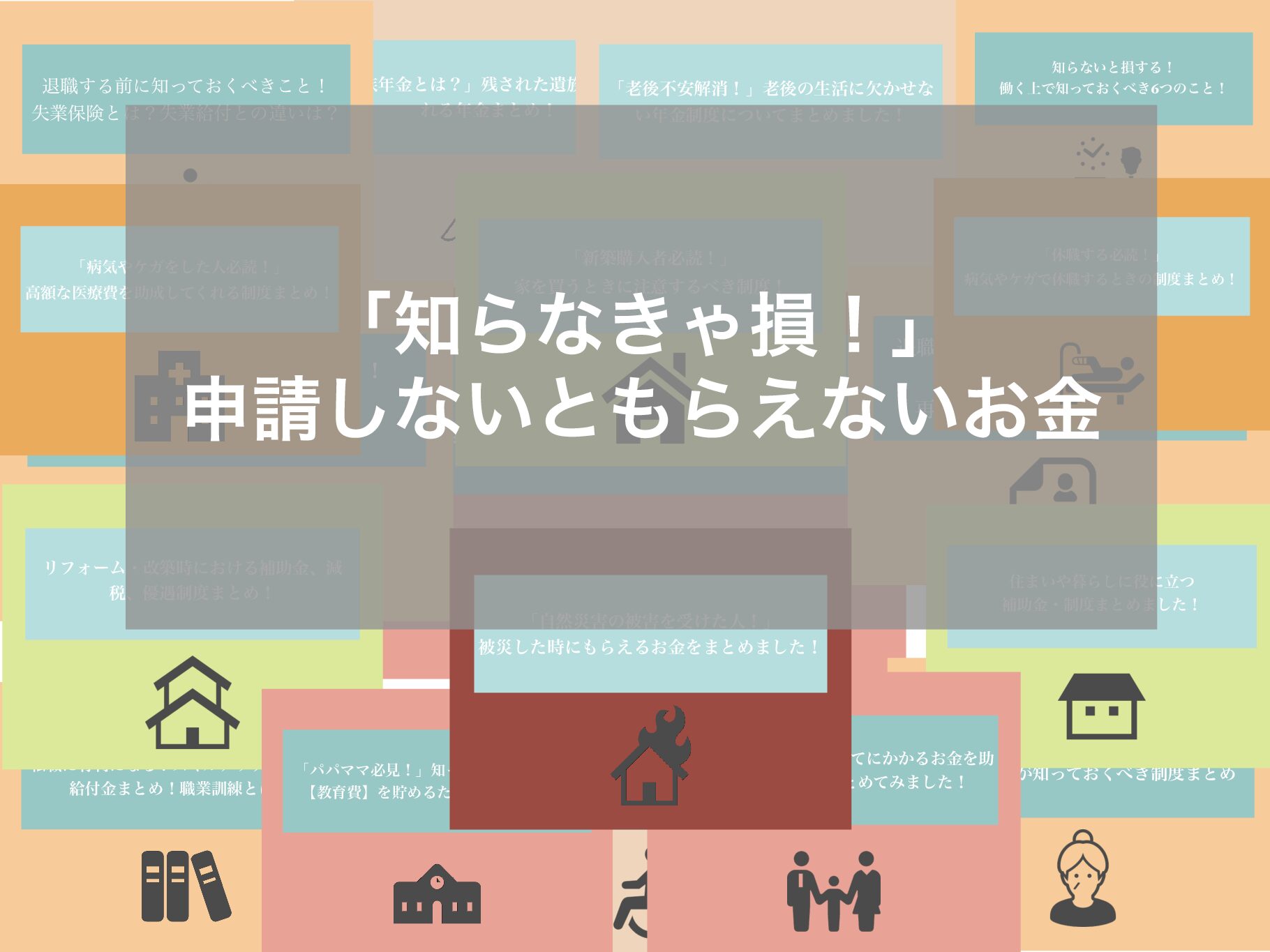こんにちわ。ダイキンです。
台風、地震、津波など自然災害は私たちが全く予期せぬ形で訪れます。特に日本は地震が多い国と言われていますので、他の国と比べて地震時への備えとする制度が整っています。
もしもの時に備えてあらかじめ把握しておきましょう。
- 被災された人
- 被災されて家族をもつ人
- 被災に備えて事前に情報を知っておきたい人
自然災害でもらえるお金はたくさんあります!
覚えておくことで、万が一が起きてもお金のことは心配しないでもいいようにしておきましょう。
被災者生活再建支援制度
自然災害で住まいが被害を受けたときに支給されます
暴風、豪雨、洪水、豪雪、高潮、地震、噴火といった一定の規模以上の自然災害で自宅や家財に大きな被害を受けると、被害の大きさや住宅の再建の仕方に応じて支援金が受けられます。
どのような人がもらえるの?
- 自然災害によって10世帯以上の住宅全壊被害が発生した市区町村で、住まいが以下のような被害を受けた人(持ち家、賃貸の両方)
- 住宅が全壊した世帯
- 住宅が半壊、または住宅の敷地に被害があり、住宅をやむなく解体した人
- 危険で居住不能な状態が長期間続いている世帯
- 大規模な補修をしなければ居住が困難な世帯
制度のポイント
被害の程度に応じて「基礎支援金」、家を再建する人にはさらに「加算支援金」が支給されます。
被害状況がわかる写真などを添付して、「り災証明書」を発行します。
それに応じて支援金額が決まります。
「基礎支援金」の申請期限は災害発生から13ヶ月、「加算支援金」は37ヶ月以内です。
災害援護資金
自然災害で世帯主が負傷した場合にお金が借りられる制度
都道府県内に災害救助法が適用された市区町村がある災害で、世帯主がケガをしたり、住居や家財が大きな被害を受けたりした場合、生活を立て直す資金として「災害援護資金」が借りられます。
借りる額には所得制限がある
災害によって負傷または居住や家財が損害を受けた人で、所得制限があり、前年の総所得額を超えないこと。
- 1人世帯・・・220万円
- 2人世帯・・・430万円
- 3人世帯・・・620万円
- 4人世帯・・・730万円
- 5人以上の世帯・・・760万円+30万円
以下1人増えるごとに30万円を足した額。
ただし、住居が滅失した場合は世帯人数に関わらず1270万円です。
融資の条件は?
世帯主の負傷と住居の損害の程度によって融資限度額が異なります。
当初3年間(特別そちが取られると5年間)は据置期間として返済しなくてもいい。
その期間は利子もないです。
返済期間は据置期間も含めて10年です。
「災害援護資金」の対象とならない人で、低所得世帯、障害者のいる世帯、要介護者のいる世帯を対象として、生活福祉資金制度による貸付もあります。
「緊急小口資金」は10万円、災害によって必要となった資金については「福祉金」150万円が目安です。
市区町村によって条件などは違うので問い合わせして確認しましょう。
災害障害見舞金
自然災害で身体、精神に障害を負った人への見舞金です。
ひとつの市区町村で居住が5世帯以上滅失されたなど、一定の被害が生じた自然災害によって、日常生活が困難になるような障害を負った場合には、「災害障害見舞金」が支給されます。
どのような人がもらえるの?
日常生活が困難な状態にある人で、具体的には以下のいずれかの条件に該当する人。
- 両目が失明した人
- 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護が必要な人
- 両上肢を膝関節以上で失った人
- 両下肢の用を全廃した人
- 精神または身体の障害が重複して障害の程度が一定以上の人
支払い上限額
生計を担っている人が障害を負った・・・上限250万円
その他の人が障害を負った・・・上限125万円
災害弔慰金
自然災害で家族を失った人に公的な弔慰金が支給されます
ひとつの市区町村で住居が5世帯以上滅失されたなど、一定の被害が生じた場合には、「災害障害見舞金」が支給されます。
どのような人がもらえるの?
自然災害によって亡くなった人の遺族。
配偶者、子、父母、孫、祖父母か、兄弟姉妹(死亡した人とど虚または生計を同じくしていた場合にのみ)
支払い上限額
生計を担っている人が死亡・・・上限500万円
その他の人が死亡・・・上限250万円
市町村によって異なりますので自治体の窓口で確認してください。
直接の被害でなくても認められれば支給されます
自然災害による家屋倒壊や津波といった直接の被害による死亡だけではなく、被災によるショックや避難所生活にストレスなど二次的な要因で死亡した時も認められればもらえます。
教育への各種支援
教科書の支給や奨学金などの支援
自然災害にあっても子どもの就学は妨げたくないですよね。
教科書の支給など、さまざまな支援があります。
教科書等の無償給与(災害援助法)
災害援助法が適用された地域では、被災した児童生徒の教科書が失われたり、使えなくなったりした場合、1ヶ月以内に無償で支給されます。
また文房具や通学用品も支給されます。
対象者は小・中学校、高等学校などの児童・生徒(特別支援学校、養護学校の小学児童、中学部生徒、中等教育学校、特別支援学校の高等部、高等専門学校、専修学校、各種学校の生徒を含む)
小・中学生の就学援助措置
被災により就学が困難となった児童・生徒の保護者を対象に、就学必要な学用品費、新入学用品費、通学費、校外活動費などを援助されます。
奨学金制度の緊急採用・応用採用
日本学生支援機構では、災害などでやむを得ず他の学校に入学することで費用が増えた場合「緊急採用(第一種奨学金)」「応用採用(第二種奨学金)」を貸与。第一種は無利子。
雑損控除・災害減免法
損害額を所得から控除して税負担を軽減
自然災害で自宅などの生活に必要なものが損害を受けた場合には、税金が軽減される「雑損こ控除」や「災害減免法」の適用を受けることができます。
「雑損控除」「災害減免法」のどちらかを選択する。
雑損控除
災害や盗難などで、地震や配偶者、扶養している親族の資産が損害を受けた場合、一定額を所得から控除できる。所得が減る分、税額が減税され、被災した年に納めた所得税が還付され、翌年の住民税が安くなる。
損害が大きい場合は最長3年間にわたって控除が受けられる。
以下のいずれか多い方を控除します。
- 【損失額】ー【保険などで補填された金額】ー【総所得金額の10%】
- 【災害関連支出(住宅などの取り壊し費用や修繕費用などの金額)】ー【5万円】
災害減免法
所得が1000万円以下で、住宅や家財の損害額が時価の50%以上の場合に適用されます。
所得が低いほど控除額が大きいです。
控除されるのは一年のみ。
控除額は以下のとおりです。
所得500万円以下の人・・・全額
所得500万円超の750万円以下の人・・・50%
所得750万円超1000万円以下の人・・・25%
まとめ
いかがでしたでしょうか?
自然災害で被災されたときは、不安な気持ちでいっぱいだと思いますが、少しでもお金面での負担をなくせるような制度を紹介しました。
最後まで読んでいただきありがとうございます。